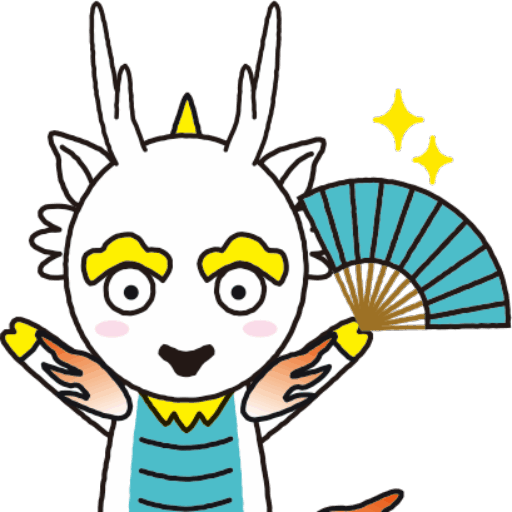歴史情報学の創成
新たな歴史学の可能性を切り開く
科学研究費 学術変革領域A
(2025年度〜2029年度)
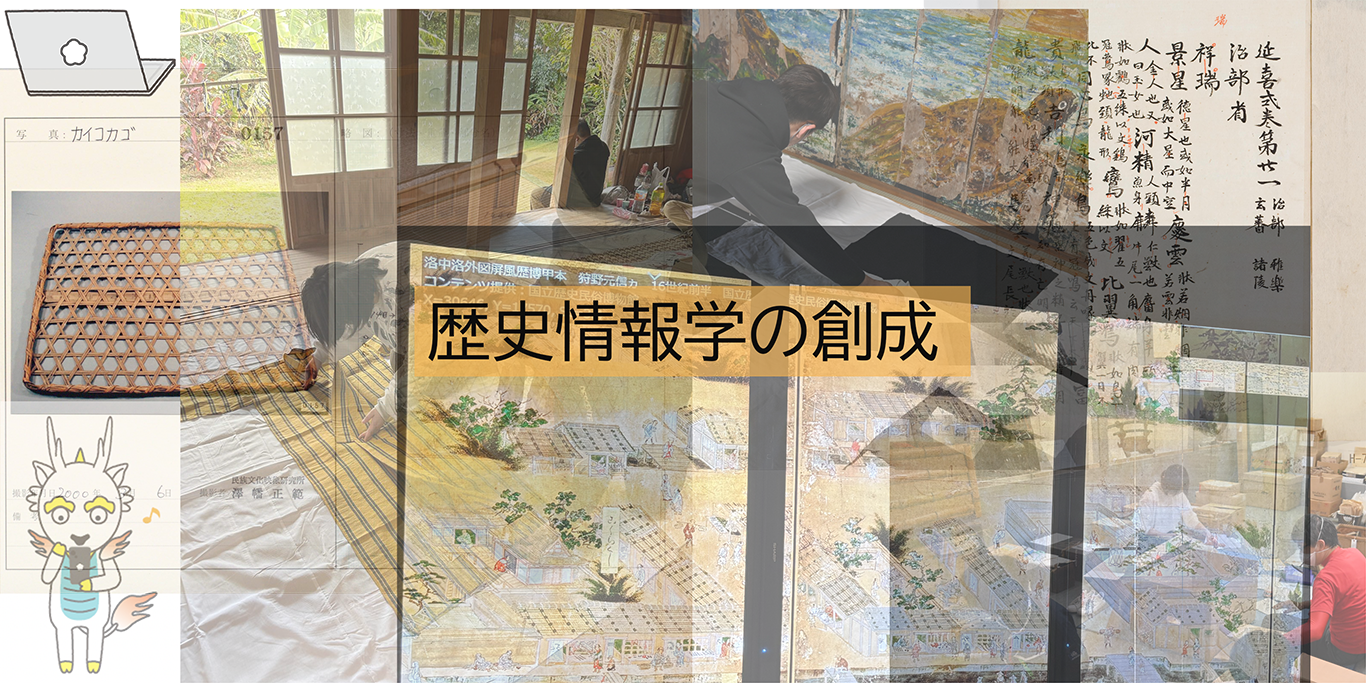
歴史情報学とは何か
人文学のさまざまな課題に対して情報技術を応用する研究をデジタルヒューマニティーズと呼びます。本研究領域では、そのデジタルヒューマニティーズの中でも歴史学を対象として、研究開発を進め、新たな学問として歴史情報学の理論と実践の体系化を目指します。
AIを含む最先端の情報学的手法とデータ基盤を積極的に活用し、従来の歴史学における知の構造を再発見し、そこから新たな歴史学への可能性を見出していきます。
コンピュータと歴史学の協業(垂直展開)
- 情報処理技術による歴史資料の解析
- 自然言語処理や機械学習を活用し、手書き資料の自動翻刻やテキスト中の固有表現抽出を実現していきます。人の解釈を補完・再現可能にする分析環境を整備し、歴史研究の高度化に貢献します。
- デジタル基盤による知の共有
- 歴史データの蓄積・公開・可視化を推進していきます。デジタル化された歴史資料の情報を通じて研究者と市民が協働できる知の循環環境を構築し、コンピュータを通じた多くのステークホルダーとの協業を実現します。
- 個人研究からチーム型・学際型研究への転換
- デジタル技術を基盤に、領域横断的な連携や共同研究体制を促進し、新たな「チーム型歴史学」の可能性を模索します。


多くの人と歴史学の協業(水平展開)
- 学際的連携による研究の高度化
- 歴史学と情報学をはじめとする複数分野の専門家が協働することで、複雑な課題への多角的なアプローチと新たな知の創出を実現します。
- 歴史資料の来歴などの記録から資料情報を豊かに
- 歴史資料のメタデータだけではなく、もの資料の来歴情報などのデータ化実践を進めます。これにより、わかりやすい資料の情報を増やすことで、歴史資料の理解を広げていきます。
- 歴史資料のデータ化などを通じ、多くの人との協業を実践
- 公共機関や地域団体との連携により、研究成果を教育・文化資源として還元し、持続的な共創のサイクルを形成。
歴史情報学領域の計画班
垂直展開と水平展開の両面を目指すべく、A項目として水平展開の計画班を、B項目として垂直展開の計画班を配置し、それぞれの課題意識に合わせて研究を進めています。そしてA項目とB項目の両者を統合する理論検討をC項目にて実施します。
A01 基盤目録構築班
誰もが入力・利用しやすい歴史資料の基盤目録のあり方を検討し、整備します。非専門家もアクセスしやすく、資料の本質を適切に記述できる高度な目録システムとは何かを考えます。
A02 歴史資料情報高度化班
歴史資料に内包された複雑な知識を整理・構造化し、ナレッジベースとして活用するための方法を開発します。資料の来歴や移動、構成の変化といった情報を対象とし、より深い資料理解を支援し、多くの人の資料の理解に役立てます。
A03 地域歴史共有班
地域住民と連携して歴史資料の保存・活用を進める歴史学の「水平展開」の実践を行う班です。実際に複数の地域を対象として、地域ごとの多様な事情・歴史的文脈に応じた歴史資料の共有と共同研究を進めます。
B01 歴史情報学解析班
いわゆるAIやOCR技術等を用いて、歴史資料のテキスト・画像などの高度な解析を実施します。特に近代初期の文書資料などに焦点を当て、資料の読解速度向上と目録作成支援を行います。加えて、機械による読解と人文学的な解釈の突き合わせなどを進めていきます。
B02 歴史知識情報構築班
歴史資料の機械可読な知識辞書を構築します。人物・時代・出来事などの歴史上の情報を構造化し、資料解析や検索に活用可能な土台を整備します。研究者だけでなく市民も知識構築に関われる仕組みも検討し、歴史学に係る情報基盤を支える材料を作ります。
B03 高度テキスト構築班
国際標準に準拠した歴史資料テキストの整備を通じて、信頼性の高い「研究に基づくデータ」の提供を進めます。資料の構造や読みの痕跡をコンピュータに記録し、「人文学の知」をタグとして可視化することを目指します。辞書情報との連携も図り「作業ではない構造化テキスト」を検討します。
C 理論班
情報学と歴史学、水平展開と垂直展開の実践成果を結びつけ、歴史学の新たな理論枠組みを構築していきます。専門家の役割や人間ならではの解釈を見つめ直し、Historian in the loopという新たな概念を設定し、歴史情報学の理論構築を目指します。